「この企画、良いと思います」「今日のランチ、何にしようかなと考える」
私たちは日常的に「思う」と「考える」という言葉を使っていますが、この2つの違いを意識したことはありますか?
実は、「思う」と「考える」には明確な違いがあり、これを理解して使い分けるだけで、仕事の評価が上がったり、人間関係がスムーズになったりするかもしれません。
この記事では、「思う」と「考える」の具体的な違いから、ビジネスシーンでの使い分け、そして「考える力」を鍛えるための具体的なステップまで、分かりやすく解説していきます。
「思う」と「考える」の基本的な意味の違い
「思う」と「考える」、どちらも頭の中で何かを巡らせる行為ですが、そのプロセスと性質は大きく異なります。違いを理解するために、まずはそれぞれの言葉が持つ基本的な意味を見ていきましょう。
一言でいうと、「思う」は感情的・直感的な心の動きであり、「考える」は論理的・分析的な頭の働きです。
「思う」は、特に深い根拠や理由がなく、心に自然と浮かんでくる感覚や感情を表します。「この夕焼け、きれいだなと思う」「なんだか胸騒ぎがすると思う」といった使い方が典型的です。これは、理屈ではなく心で感じている状態といえるでしょう。英語では “I feel” や、個人的な感想を述べる際の “I think” に近いニュアンスです。ただし、英語の “I think” は文脈によって日本語の「考える」に対応する場合もあります。
一方、「考える」は、筋道を立てて答えを導き出す知的な作業を指します。課題の原因を分析したり、複数の選択肢を比較検討したり、計画を立てたりする行為がこれにあたります。「どうすればこの問題を解決できるか考える」「旅行の最適なルートを考える」など、目的を持って頭を働かせ、結論を出すプロセスが含まれます。英語では “I consider” や “I analyze” が近い表現となります。
一目でわかる!「思う」と「考える」の比較表
言葉での説明だけでは、まだ少し掴みづらいかもしれません。そこで、「思う」と「考える」の違いを項目別に整理し、比較表にまとめてみました。これで、2つの言葉のキャラクターの違いが、よりクリアになるはずです。
| 項目 | 思う (Feel / Think) | 考える (Consider / Analyze) |
|---|---|---|
| 性質 | 主観的・感情的・感覚的 | 客観的・論理的・分析的 |
| プロセス | 心に自然と浮かぶ | 筋道を立てて答えを出す |
| 根拠 | 不要・曖昧 | 必要・明確 |
| 時間 | 瞬間的・短時間 | 比較的時間がかかる |
| 脳の働き | 感覚や感情に関わる領域がより活発 | 理性や分析に関わる領域がより活発 ※実際の脳の働きは複雑で、両者は相互に関連しています |
| 英語表現 | I feel, I think (感想・印象として) | I think (論理的に), I consider, I analyze, I figure out ※英語の”I think”は文脈により「思う」「考える」両方に対応 |
| 具体例 | 「この曲、好きだなと思う」 「明日は晴れるといいなと思う」 | 「なぜ売上が落ちたのか考える」 「A案とB案のメリット・デメリットを考える」 |
このように並べてみると、両者の違いは一目瞭然ではないでしょうか。「思う」が心(ハート)の働きだとすれば、「考える」は頭(ヘッド)の働きとイメージすると分かりやすいかもしれません。ただし、実際の脳の働きでは、感情と理性は密接に関わり合っており、完全に分離できるものではありません。
どちらが良い・悪いというわけではなく、それぞれに役割があります。大切なのは、場面に応じて適切に使い分ける意識を持つことです。
なぜ「思う」と「考える」の使い分けが重要なのか?
「思う」と「考える」の違いが分かったところで、次に「なぜ、その使い分けが重要なのか?」という点について掘り下げていきましょう。実は、この使い分けを意識するだけで、仕事やプライベートに大きなメリットが生まれます。
ビジネスシーンでの重要性
ビジネスの世界では、「考える」ことの価値が特に高まります。例えば、会議で意見を求められたとき、「この企画は良いと思います」とだけ答えるとどうでしょうか。これでは、ただの感想に聞こえてしまい、「なぜ良いのか」「具体的な根拠は何か」という点が伝わりません。自信がなく、無責任な印象を与えてしまう可能性すらあります。
ここで、「〇〇というデータに基づき、この企画には3つのメリットがあると考えます」と表現を変えるだけで、印象は大きく変わります。筋道を立てて分析した「考え」であることが伝わり、意見に説得力と信頼性が生まれるのです。
報告書や提案書でも同様です。「〜だと思います」という表現は避け、「〜と考えられます」「〜と結論付けました」といった言葉を選ぶことで、客観的で論理的な思考ができる人材として評価されやすくなるでしょう。
コミュニケーションを円滑にする
プライベートな人間関係においても、この使い分けは役立ちます。相手が「〇〇だと思うんだよね」と話しているときは、共感や感想を求めていることが多いでしょう。それに対して「いや、それは論理的に考えると…」と返してしまうと、話の腰を折ってしまうかもしれません。相手が「思う」モードのときは、まず「そう思うんだね」と受け止めるのがスムーズです。
逆に、何か問題を相談されて「どうしたらいいか一緒に考えてほしい」と言われた場合は、相手は具体的な解決策や客観的なアドバイスを求めています。このときは、感情論ではなく、問題点を整理し、解決策を一緒に「考える」姿勢が大切になります。
自分の意図を伝える際も同じです。ただの感想なら「思う」、提案や意見なら「考える」と使い分けることで、相手に誤解なく真意を伝えられます。
デカルトの二元論とは?心身問題への示唆に迫る【我思う、ゆえに我あり】
「思う」から「考える」へ!思考力を鍛える3つのステップ
「自分はつい『思う』だけで済ませてしまうことが多いかも…」と感じた方もいるかもしれません。しかし、心配は不要です。「考える力(論理的思考力)」は、継続的なトレーニングによって多くの人が向上させることができます。個人差はありますが、意識的に練習することで着実に成長できるでしょう。ここでは、今日から実践できる簡単な3つのステップをご紹介します。
ステップ1:問いを立てるクセをつける
思考の第一歩は、「問い」から始まります。何かを感じたり、情報に触れたりしたときに、「なぜだろう?」「本当にそうなの?」「具体的にはどういうこと?」と自分に問いかけるクセをつけましょう。
例えば、ニュースを見て「面白いなと思う」で終わらせるのではなく、「なぜ自分はこれを面白いと感じたんだろう?」「この出来事の背景には何があるんだろう?」と一歩踏み込んで自問自答してみるのです。この小さな「なぜ?」の繰り返しが、物事の表面だけでなく、本質を見るための深い思考へと繋がっていきます。
最初は面倒に感じるかもしれませんが、自分のペースで継続していけば、徐々に自然にできるようになります。無理をせず、できる範囲から始めることが大切です。
ステップ2:情報を集めて整理する
自分の直感や感想(思う)だけで判断するのではなく、客観的な情報を集めて判断材料とするのが「考える」プロセスです。問いを立てたら、それに対する答えを探すために、本やインターネット、専門家の意見など、複数の情報源からフラットに情報を集めましょう。
そして、集めた情報をただ眺めるだけでは不十分です。情報同士の関係性を明らかにしたり、共通点や相違点でグループ分けしたりして、頭の中を整理整頓する必要があります。紙に書き出したり、マインドマップを使ったりするのも非常に効果的です。情報を構造化することで、全体像が把握でき、より的確な結論を導き出しやすくなります。
ステップ3:根拠を持って結論を出す
情報が整理できたら、最後は自分なりの結論を導き出すステップです。ここで重要なのは、「なぜその結論に至ったのか」という根拠を明確にすることです。
「A、B、Cという情報から、私は〇〇だと考えます。その理由は3つあり、1つ目は…」というように、誰かに説明できる形で結論を言語化する練習をしましょう。この「根拠(理由)→結論」のセットで話すことを意識するだけで、あなたの意見は格段に論理的になります。最初はうまくできなくても、繰り返し練習することで、説得力のある「考え」を述べられるようになるはずです。
「削除」と「消去」の違いとは?意味や使い分けを分かりやすく解説
まとめ
今回は、「思う」と「考える」の違いについて、意味や使い分け、そして「考える力」の鍛え方まで解説しました。
- 思う:直感的・感情的な心の動き。個人の感想。
- 考える:論理的・分析的な頭の働き。筋道を立てて結論を出すプロセス。
この2つは、どちらが優れているというものではなく、車の両輪のようなものです。豊かな感性で「思う」ことと、冷静な理性で「考える」こと。両方をバランス良く使いこなすことが、仕事や人生をより豊かにする鍵となります。
まずは、普段の会話や仕事の中で、「今、自分は『思って』いるのか、それとも『考えて』いるのか?」と少しだけ意識を向けることから始めてみるのもいいですね。その小さな意識が、あなたの思考を一段階レベルアップさせるきっかけになるはずです。
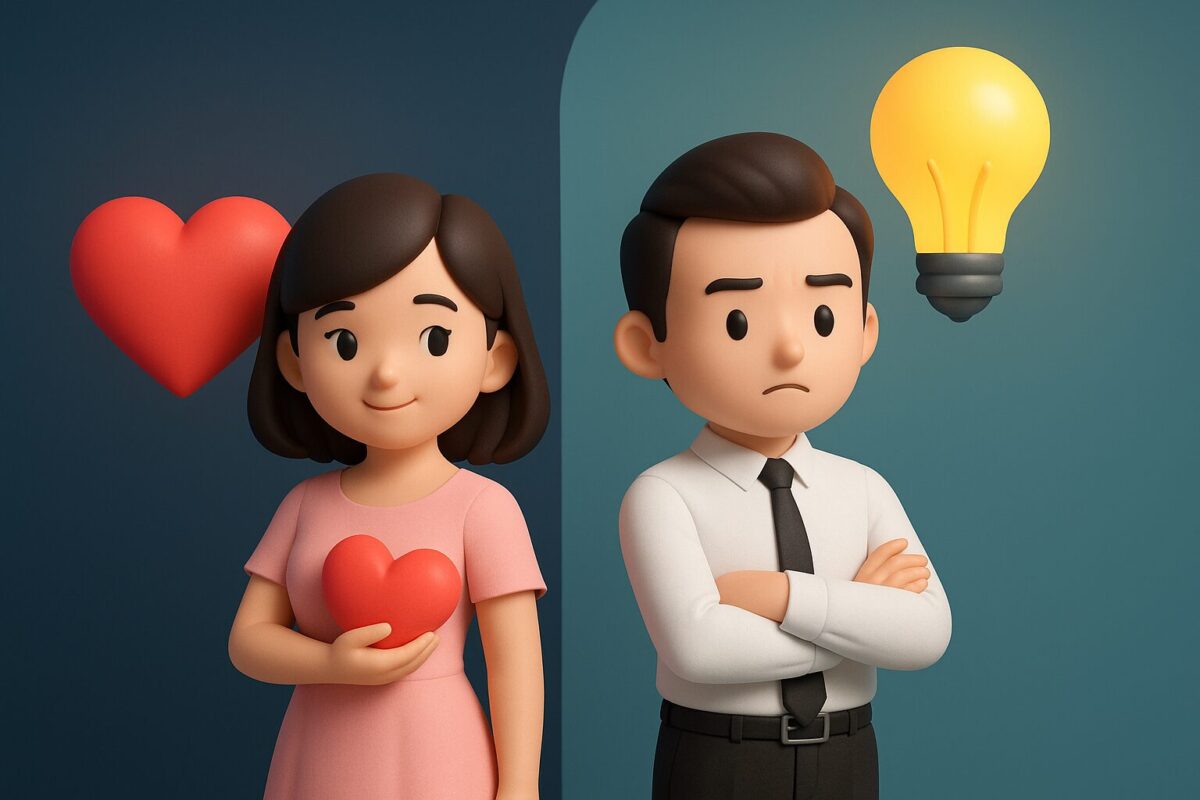
コメント