「再就職したいけれど、アピールできるスキルがない」
「勉強したいけれど、生活費が不安でスクールに通えない」
このような悩みを抱え、一歩踏み出せずにいませんか?
実は、国の制度を使えば「月10万円」の給付金を受け取りながら、無料で専門スキルを学ぶことが可能です。それが「求職者支援訓練(ハロートレーニング)」です。
この記事では、制度の仕組みや対象者、メリット・デメリット、そして給付金を受け取るための詳細な条件を分かりやすく解説します。
結論から言うと、雇用保険(失業保険)を受給できない人にとって、これ以上ないほど強力なセーフティネットです。制度を正しく理解して、新しいキャリアへの第一歩を踏み出しましょう。
求職者支援訓練とは?雇用保険がない人のための制度
求職者支援訓練とは、再就職や転職を目指す人が、月10万円の生活支援給付金を受給しながら、無料(テキスト代などは実費)で職業訓練を受けられる国の制度です。
最大の特徴は、「雇用保険(失業保険)を受給できない人」を主な対象としている点にあります。
一般的に、会社を辞めた直後の人は失業保険をもらいながら生活できますが、以下のような人はその支援を受けられません。
- 雇用保険の加入期間が足りない人
- 失業保険の受給期間が終了した人
- 自営業を廃業した人
- 専業主婦(夫)から正社員を目指す人
- フリーランスや学生で就職先が決まっていない人
こうした方々が、生活費の心配を減らしつつスキルアップに専念できるよう設計されています。
※制度の利用には、ハローワークへの求職申し込みが必要です。
公共職業訓練との違い【比較表】
ハローワークには「公共職業訓練」という似た制度があります。どちらも愛称は「ハロートレーニング」ですが、対象者が明確に異なります。
自分がどちらに該当するのか、以下の表で確認してみましょう。
| 項目 | 求職者支援訓練 | 公共職業訓練 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 雇用保険を受給できない人 | 雇用保険を受給している人 |
| 受講料 | 無料(テキスト代等は自己負担) | 無料(一部有料コースあり) |
| 生活支援 | 職業訓練受講給付金 (月10万円+交通費など) | 失業保険(基本手当) (受給期間の延長措置あり) |
| 運営主体 | 民間教育機関(専門学校など) | 国・都道府県・ポリテクセンター |
| コースの特徴 | 基礎~実践まで幅広い (IT、事務、介護、美容など) | ものづくり、技術系が多い (機械加工、電気設備など) |
このように、失業保険がないなら「求職者支援訓練」、あるなら「公共職業訓練」と覚えておけば間違いありません。迷った場合はハローワークの窓口で相談すれば、適切な方を案内してもらえます。
【重要】月10万円の給付金をもらうための条件
求職者支援訓練の最大の魅力は「職業訓練受講給付金」です。
しかし、訓練自体は誰でも受けやすい一方、給付金を受け取るための条件は非常に厳格です。
以下の要件をすべて満たす必要があります。
収入・資産に関する条件
経済的な支援が本当に必要な人に届けるため、細かい数字の基準が設けられています。
- 本人収入が月8万円以下であること(シフト制のアルバイトなどで月によって変動する場合、特例判定があるケースもあります)
- 世帯全体の収入が月30万円以下であること
- 世帯全体の金融資産が300万円以下であること
- 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していないこと
ここでの「世帯」とは、同居している配偶者や親なども含みます(住民票や生計の実態で判断されます)。
訓練受講に関する条件
真面目に訓練に取り組む意思があるかどうかも問われます。特に過去の受給歴に関する条件は重要です。
- 全ての訓練実施日に出席すること
- 世帯の中に同時にこの給付金を受けている人がいないこと
- 過去6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けていないこと
- 過去3年以内に不正受給をしていないこと
特に「全ての訓練実施日に出席」という点が重要です。これについては後述するデメリットの項目で詳しく解説します。
求職者支援訓練のメリットと金銭的サポート
条件をクリアできれば、この制度は求職者にとって大きなチャンスとなります。主なメリットと、給付金以外の金銭的サポートについて紹介します。
無料で専門的なスキルが身につく
通常、民間のスクールに通えば数十万円かかるWebデザイン、プログラミング、医療事務などの講座を受講料無料で受けられます。
自己負担はテキスト代や補講費(数千円〜1万円程度)のみです。金銭的なリスクを負わずに、未経験の業界へチャレンジできるのは最大の強みといえるでしょう。
働きながらでも受講できる
失業保険の場合、受給中にアルバイトをすると支給額が減額されたり、支給が先送りになったりすることがあります。
一方、求職者支援訓練の給付金は、「月8万円以下」かつ「訓練に支障がない範囲」であれば、アルバイト収入があっても満額(10万円)受け取れます。
「週2〜3日アルバイトをしつつ、残りの日は訓練で学ぶ」といった柔軟な生活設計が可能です。
交通費や寄宿手当も支給される
月10万円の受講給付金とは別に、訓練校へ通うための諸手当も支給されます。
- 通所手当(交通費):最も経済的かつ合理的と認められた経路の運賃(月額上限42,500円)
- 寄宿手当:訓練を受けるために同居の家族と別居して寄宿(下宿など)が必要と認められた場合(月額10,700円)
※交通費等は必ずしも全額支給とは限らない点にご注意ください。
生活費が不足する場合は「貸付制度」も利用可能
もし、給付金(月10万円)とアルバイト収入だけでは生活費が足りない場合、希望者は「求職者支援資金融資」という貸付制度を利用できる可能性があります。
- 貸付額:単身者 月5万円 / 扶養家族がいる方 月10万円
- 条件:利率 年2.0%(信用保証料を含む)、担保・保証人不要
あくまで「借入金」なので返済が必要ですが、当面の生活を安定させ、訓練に集中するための選択肢として用意されています。
知っておくべきデメリットと注意点
メリットばかりに目を向けて安易に申し込むと、後悔することになりかねません。特に注意すべき「厳しさ」について解説します。
出席要件が非常に厳しい
給付金をもらうためには、原則として「100%の出席」が求められます。
風邪や身内の不幸など「やむを得ない理由」がある場合でも、病院の領収書などの証明書を提出した上で「8割以上の出席」が必要です。
もし、寝坊やサボりなどの「やむを得ない理由以外」で1日でも欠席すると、その支給単位期間(1ヶ月分)の給付金は全額不支給となります。
遅刻や早退も3回で欠席1回とカウントされるなど、管理は徹底されています。「少しぐらい休んでも大丈夫だろう」という甘い考えは通用しません。
希望のコースが開講されているとは限らない
訓練コースは地域や時期によってバラつきがあります。
「Webデザインを学びたいのに、近所では介護のコースしか募集していない」「次の開講は3ヶ月先だった」というケースも珍しくありません。
また、人気のコース(特にIT・Web系)は倍率が高く、面接や筆記試験の選考で落ちてしまうこともあります。
訓練内容のレベルが合わない可能性
求職者支援訓練は、未経験者を対象とした基礎的なカリキュラムが多く組まれています。そのため、以下のようなミスマッチが起きる可能性があります。
- 経験者には物足りない:すでにある程度の知識がある場合、授業の進度が遅く感じる。
- 初心者でも難易度が高い:IT系コースなどで、パソコンの基本操作ができないまま参加するとついていけない。
ミスマッチを防ぐため、応募前に必ず訓練校の「施設見学会」や「説明会」に参加し、カリキュラム詳細や授業の雰囲気を確認しましょう。
不正受給へのペナルティが重い
収入をごまかしたり、嘘の理由で欠席をごまかしたりして給付金を受け取った場合、厳しい処分が待っています。
- 支給された給付金の全額返還
- さらにその2倍の額の納付(いわゆる3倍返し)
- 詐欺罪として処罰される可能性
アルバイトの日数や収入額などは、必ず正直に申告しましょう。
受講者のリアルな評判・口コミ
実際に制度を利用した人の感想は、これから受講を考える上で重要な判断材料になります。良い評判と注意が必要な評判の両方を見てみましょう。
良い評判・口コミ
- 「独学で挫折したが、学校に通うことで強制力が働きスキルを習得できた」
- 「同じ目標を持つ仲間と励まし合いながら就職活動ができた」
- 「生活費の心配をせずに勉強に集中できる環境がありがたかった」
- 「先生が親身に相談に乗ってくれ、未経験でも自信がついた」
注意が必要な評判・口コミ
- 「クラスによって受講生のモチベーションに差があり、雰囲気に馴染めなかった」
- 「基礎的な内容が多く、期待していたほど実務レベルには達しなかった」
- 「就職支援が手厚い反面、就職へのプレッシャーを強く感じることもあった」
評判は、受講するコースやクラスメイト、担当講師によって大きく変わります。ネットの口コミを鵜呑みにせず、必ず自分の目で説明会に行って確かめることが大切です。
どのような訓練コースがあるのか
訓練期間は2ヶ月〜6ヶ月程度が一般的です。内容は「基礎コース」と「実践コース」に分かれています。
【コースの一例】
- IT・Web系:Webクリエイター、プログラミング、SNSマーケティング
- 事務系:医療事務、調剤薬局事務、経理・簿記、OA事務
- 介護・福祉系:介護職員初任者研修、実務者研修
- サービス系:ネイリスト養成、エステティシャン、観光ビジネス
最近では、通学の負担を減らすためにオンライン受講が可能なコースも増えています。
自分の住んでいる地域でどのような訓練が募集中か、まずは検索してみることをおすすめします。
申し込みから受講開始までの流れ
「受講してみたい」と思ったら、早めにハローワークへ行くことが大切です。手続きには時間がかかります。
- ハローワークで相談・求職申込窓口で「求職者支援訓練を受けたい」と伝えます。
- コース選び・受講申込書の提出希望のコースを決め、ハローワークへ申込書を提出します。
- 訓練実施機関による選考面接や筆記試験を受けます。
- 合格・受講あっせん合格後、再度ハローワークへ行き「受講あっせん(受講指示)」を受けます。
- 訓練開始月に1回、ハローワークで「指定来所日」があり、職業相談と給付金の申請を行います。
参考:職業訓練受講給付金の手続き方法と「厳しい審査を通すコツ」|求職者支援訓練の条件とは
まとめ:制度を賢く利用してスキルアップしよう
求職者支援訓練は、金銭的な不安を解消しながら、再就職への切符を掴める素晴らしい制度です。
この記事の要点まとめ:
- 対象者:雇用保険がない人(フリーター、主婦、自営業廃業など)
- メリット:受講料無料、月10万円の給付金、就職サポート
- 注意点:過去6年以内の受給歴なし、世帯月収30万円以下などの条件あり
- 覚悟:出席管理は厳格。本気で就職したい人向け
「自分は対象になるかな?」「どんなコースがあるのかな?」と気になった方は、まずは最寄りのハローワークへ足を運び、窓口で相談してみてください。
今の状況を抜け出し、自信を持って働くための第一歩は、そこから始まります。
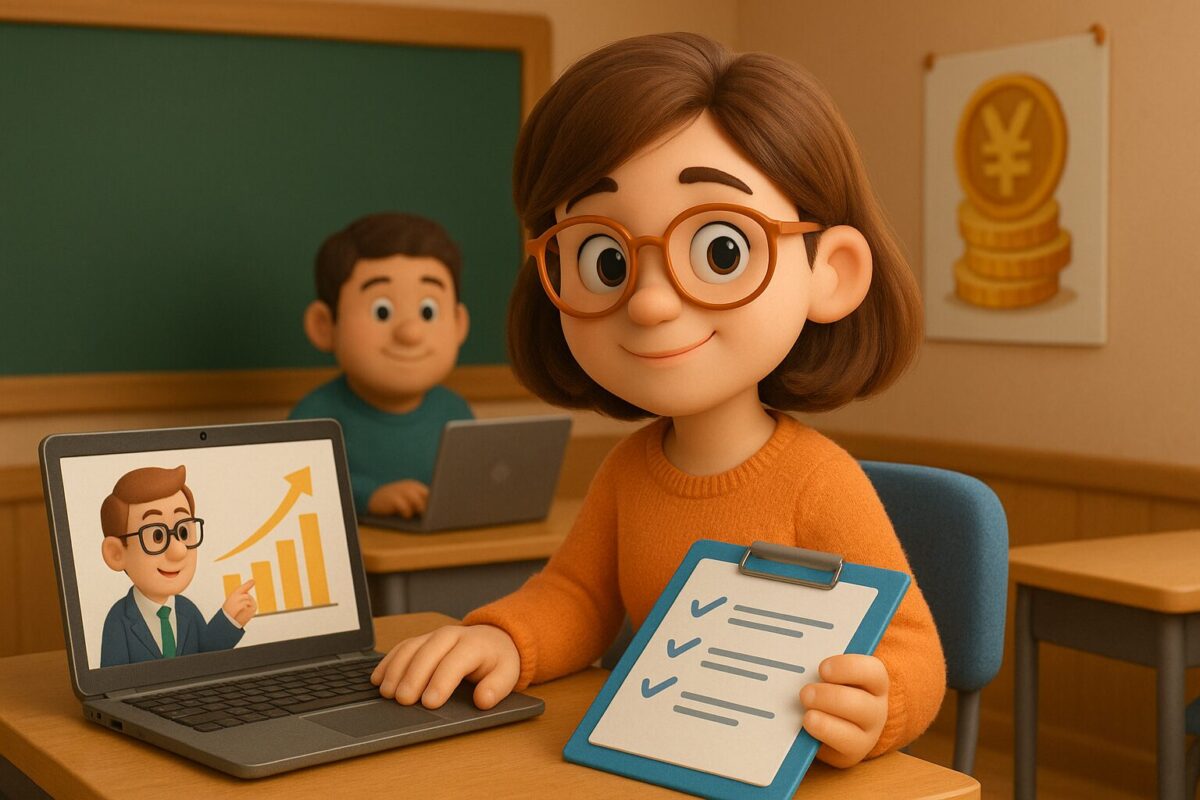
コメント