新聞を「1部」と数えたり、「1枚」と数えたり。この違い、ご存知ですか?
結論から言うと、新聞は「何を数えるか」で単位が変わります。
この記事では、「部」「枚」「紙」「面」「号」といった新聞の数え方の違いを、比較表も使いながら分かりやすく解説します。
【比較表】新聞の数え方「部」「枚」「紙」の違いが一目瞭然
新聞の数え方で特に混同しやすいのが、「部(ぶ)」「枚(まい)」「紙(し)」の3つです。
まずはこの3つの違いを、比較表で確認してみましょう。
| 単位 | 読み方 | 数える対象 | 意味・ニュアンス | 使い方の例 |
|---|---|---|---|---|
| 部 | ぶ | 発行された新聞(一式) | ひとまとまりの商品として完成したもの | 「コンビニで新聞を1部買う」 「A新聞は100万部発行されている」 |
| 枚 | まい | 新聞を構成する紙 | 物理的な紙そのもの | 「新聞紙を1枚使って窓を拭く」 「チラシが3枚入っていた」 |
| 紙 | し | 新聞の種類(銘柄) | 新聞社やブランドのラインナップ | 「我が家は2紙購読している」 「主要5紙の社説を読む」 |
このように、数える対象が全く異なることが分かりますね。
「1部」は、私たちがお店で買ったり、朝ポストに届いたりする「新聞ひとそろい」のことです。
「1枚」は、その「1部」をバラバラにしたときの、物理的な「紙」のこと。
そして「1紙」は、「A新聞」「B新聞」といった新聞の「種類」を指します。
日常で最もよく使うのは「部」かもしれませんが、それぞれの違いを知っておくと、ビジネスシーンや会話の中で役立ちますよ。
新聞の「ひとまとまり」を数える基本単位「部」
新聞の数え方として最も一般的なのが「部(ぶ)」です。
これは、朝刊や夕刊など、ひとつの商品として綴じられ、発行された「ひとまとまり」を数える単位。いわば「1セット」というニュアンスですね。
「発行部数」や「販売部数」といった言葉をニュースなどで耳にすることも多いでしょう。これは、その新聞がどれくらいの「まとまり(セット)」として世に出ているかを示す数字です。
私たちが駅の売店やコンビニで新聞を買うときも、「1部ください」というのが正しい使い方になります。
なぜ「部」と数えるのかについては諸説ありますが、印刷物や書類のセットを「部」と数える慣習(例:「企画書を3部コピーする」)から来ていると考えられます。新聞も、複数の紙面(ページ)から構成される「ひとまとまりの印刷物」ですからね。
ちなみに、家庭で新聞を購読する場合、「1世帯で1部」というのが基本ですが、事務所と自宅で同じ新聞を購読していれば「2部契約している」といった数え方になります。
このように、「部」は新聞を「商品単位」「契約単位」で数えるときの基本の単位だと覚えておきましょう。
ページの数え方は「面」、紙の枚数は「枚」
次に、新聞の「中身」に関する数え方、「面(めん)」と「枚(まい)」を見ていきましょう。この2つは、新聞の物理的な構造と密接に関係しています。
まず「面」ですが、これは単純に新聞の「ページ」のことです。
「1面トップ記事」や「社会面」「スポーツ面」「テレビ面(ラテ欄)」といった言葉でおなじみですね。本や雑誌の「ページ」と同じ意味で使われますが、新聞業界では伝統的に「面」と呼ぶのが一般的です。
一方で「枚」は、前述の比較表の通り、物理的な「紙」を数える単位。
ここで少しややこしいのが、新聞の構造です。
新聞は通常、大きな1枚の紙(全紙)に4ページ(4面)分の内容を印刷し、それを真ん中で二つ折りにしています。
つまり、新聞紙を広げてみると、「1枚」の紙に「1面」「2面」「最終面から1つ手前の面」「最終面」といった形で、合計4つの「面(ページ)」が印刷されているわけです(※新聞の構造によります)。
ですから、「新聞1枚を使って工作する」と言った場合、それは「4ページ(4面)分の紙を使う」という意味になります。
「1部」の新聞(例:朝刊)は、この「枚」が何枚も重ねられて構成されている、ということですね。
掃除や梱包材として使うときは「枚」、読むときは「面」と意識すると分かりやすいかもしれません。
新聞の種類なら「紙」、発行の順番は「号」
最後に、「紙(し)」と「号(ごう)」という単位をご紹介します。これらは、これまで解説した「部」や「枚」とは、また違った側面から新聞を数える言葉です。
「紙(し)」は、新聞の「種類」や「銘柄」を数える単位です。
例えば、「A新聞とB新聞の2紙を購読している」といった使い方をします。これは「2種類の新聞(銘柄)を読んでいる」という意味ですね。
報道などで「関係者によると(A紙)」といった表記を見たことがあるかもしれません。これも「A新聞という種類の新聞」を指しています。
「全国紙」「地方紙」「経済紙」「スポーツ紙」といった分類で、「主要5紙(朝日・毎日・読売・日経・産経)」のように使われることも多いです。
もう一方の「号(ごう)」は、雑誌と同じように、創刊からの「発行の通し番号」を指す単位です。
新聞の1面(または最終面)の隅を見ると、「第〇〇〇号」といった番号が小さく記載されているはずです。これが創刊から何番目に発行された新聞かを示しています。
「創刊号」や「1万号記念」といった形で使われることが多いですね。
ちなみに、大きなニュースや事件があったときに街で配られる「号外」は、この通し番号(号)の「外」で臨時発行されるため、そのように呼ばれています。
「紙」は新聞のブランド名を、「号」は発行の歴史を数える単位、と理解しておくと良いでしょう。
【豆知識】新聞広告の「段」って何?
新聞の数え方に関連して、広告の世界で使われる「段(だん)」という単位も知っておくと面白いですよ。
新聞の紙面をよく見ると、記事が縦のブロック(コラム)に分かれていますよね。この縦のブロックのことを「段」と呼びます。
新聞広告のサイズは、この「段」を基準に決められます。
例えば、紙面の一番下(足元)にある横長の広告枠は、「5段広告」と呼ばれたりします。これは、縦の長さを「5段分」使っているという意味です。
広告の「段」の数え方と料金
新聞の紙面が縦に何段で構成されているかは、現在、新聞社によって異なります。
かつては縦15段で分割するのが主流でしたが、2000年代以降、文字を大きくするなどの紙面リニューアルに伴い、12段制や13段制を採用する新聞社が多くなってきました。
広告のサイズは、この「段」を基準に計算されます。
例えば、かつて主流だった15段制の場合、1ページ丸ごとの広告は「全15段広告」と呼ばれました。これが最も大きく、インパクトのある広告枠ですね。
当然ですが、この「段」の数が大きければ大きいほど(=広告の面積が広いほど)、広告料金は高くなります。
「5段1/2」といった数え方もあり、これは「5段分のスペースの、さらに横幅半分」といった意味になります。
まとめ
新聞の数え方、「部」「枚」「紙」「面」「号」、そして「段」。
たくさんの単位があって難しく感じたかもしれませんが、それぞれが指している対象が違うことを整理できたでしょうか。
- 部:ひとまとまりの新聞(商品セット)
- 枚:物理的な紙
- 紙:新聞の種類(銘柄)
- 面:ページのこと
- 号:発行の通し番号
- 段:広告のサイズ(縦の長さ)
これでもう、新聞の数え方で迷うことはありませんね。
日本語の奥深さを感じつつ、日常生活やビジネスシーンで、ぜひスマートに使い分けてみてください。
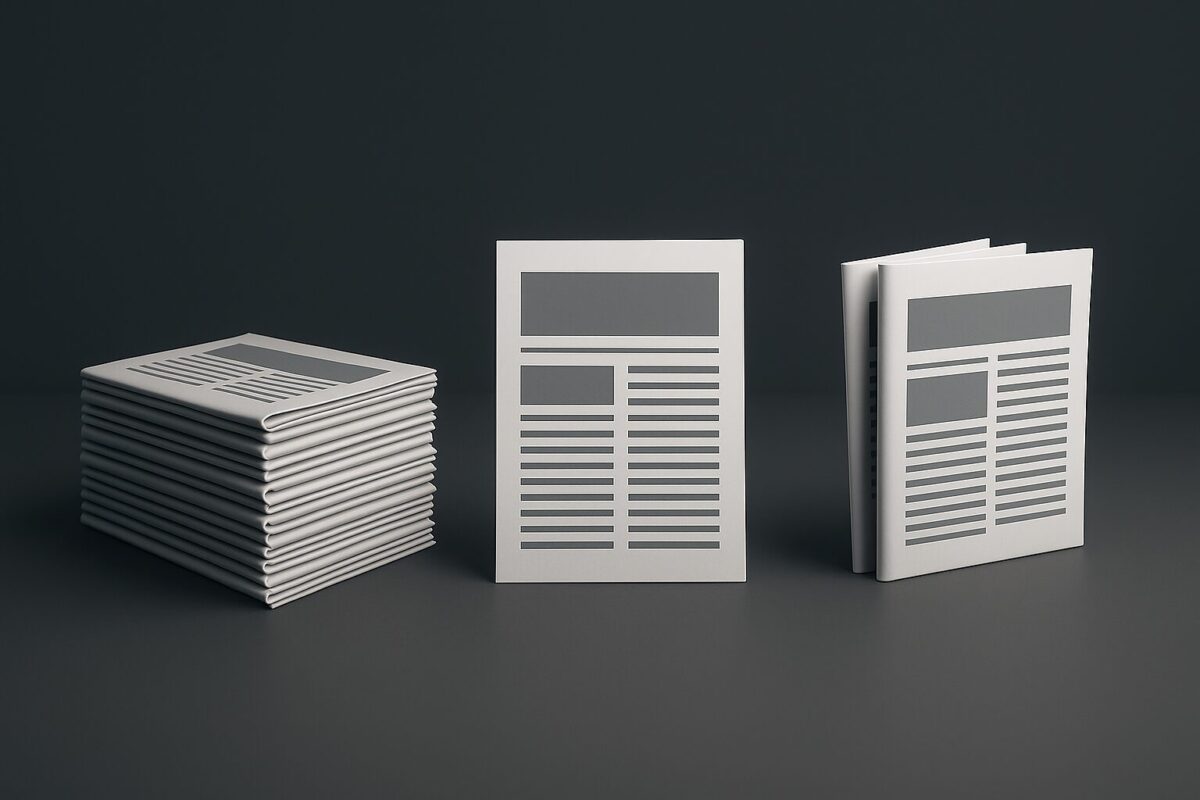
コメント