簿記資格には大きく分けて3種類があります。それぞれの主催団体と、試験の主な特徴は下記のとおりです。
- 日商簿記(日本商工会議所)
- 全商簿記(全国商業高等学校協会)
- 全経簿記(全国経理教育協会)
同じ「簿記検定」でも、出題内容や想定受験者層が異なるため、難易度や就職での評価に差が出てきます。そこで本記事では、それぞれの試験の特徴や難易度、就職への有用性などを整理しながら分かりやすく紹介します。
主催団体と受験者層の違い
日商簿記(日本商工会議所)
- 社会人や大学生を中心に、幅広い層の受験者がいる
- 企業での知名度や社会的評価が非常に高い
- 1級合格者は「税理士試験の受験資格」取得に役立つが、大学卒業などの学歴要件との組み合わせが必要になる点に注意
- 大学の商学部生や会計専門学校生が多く受験しており、合格までに1~2年かけてじっくり学習するケースが多い(かなりの勉強時間が必要)
全商簿記(全国商業高等学校協会)
- 商業高校生がメインの受験者層
- 高校在学中の学習内容と直結しており、学校を会場に実施されることが多い
- 1級に合格すると大学入試での優遇(推薦など)を受けられる場合もある
全経簿記(全国経理教育協会)
- 専門学校の学生や社会人が多く受験
- 「上級」に合格すると、税理士試験の受験資格(やはり日商簿記1級と同等)を得られる
- 試験日程が年4回(1~3級)あるなど、比較的多い回数で実施しているため受験タイミングを合わせやすい
難易度と試験範囲の違い
同じ級でも、主催団体ごとに試験範囲や問題の傾向が異なり、実質的な難易度に差があります。特に近年の日商簿記では、改定により「実務に即した内容」が増え、難易度が高まっています。以下はあくまでも一般的なイメージです。
- 日商簿記
- 1級:理論・計算ともに高度で、企業会計原則や連結会計なども扱う。「難関資格」のひとつで、合格率は10%前後(試験回によって上下)。専門学校や大学で1年~2年かけて学習する人も多い
- 2級:商業簿記・工業簿記が出題。合格率は10~30%前後(回によって変動)。改定後は実務的な問題が増えている
- 3級:基礎的な商業簿記中心。合格率は40~50%前後が一般的
- 全商簿記
- 1級:会計と原価計算の2科目受験が必要。日商簿記2級~1級の中間レベルとされることが多い
- 2級:商業簿記のみで、合格率は60~70%と比較的高め
- 3級:さらに基礎的な商業簿記
- 全経簿記
- 上級:日商簿記1級よりはやや合格しやすいとされるが、合格率は約20%と難関
- 中級:1級と上級の中間レベルで、専門学校などで中継ぎ的に導入されることがある。受験者数は少ないが、公式に認定されている等級
- 1級:商業簿記・会計学、原価計算・工業簿記の2科目。日商2級と同程度~やや上くらい
- 2級:商業簿記・工業簿記の2科目
- 3級:商業簿記の基礎
- 基礎簿記会計:まったくの入門レベル
就職・転職に有利なのはどれ?
評価が高いのは「日商簿記」
企業の採用担当者が最も認知しているのは「日商簿記」です。日商2級以上は「経理実務ができる・数字に強い」と判断される傾向が強く、事務職や経理職以外の応募でも一定のアピールにつながることがあります。
「全商簿記」「全経簿記」も価値はある
全商簿記と全経簿記も、学習内容は基本的に簿記の理論・実務を網羅しているため、決して無意味ではありません。ただし一般企業での認知度という点では、日商簿記には及ばないケースが多いのが現状です。「高校在学中に全商簿記を取得」など、自身の学習歴を示す目的ならしっかりアピールできる資格といえます。
日商簿記1級や全経簿記上級で税理士試験の受験資格を得たい場合
- 日商簿記1級合格+大学卒業などの学歴要件の組み合わせで、税理士試験の受験資格を満たすのが一般的
- 全経簿記上級合格でも、やはり大学卒業等との要件をあわせて満たすことが必要
- ただし学歴要件のない方が税理士を目指す際は「実務経験」等の別ルートが必要になるケースがあるため、要確認
履歴書に書ける級は?
実務的に評価されやすいラインとしては、
- 日商簿記:2級以上
- 全商簿記:1級(会計+原価計算の合格)
- 全経簿記:1級または上級
もちろん3級でも書けますが、「即戦力アピール」という点では2級以上を取得しておくのが安心です。
最新の受験料や合格率(あくまで目安です)
下記の数値は年度や試験回によって変動があるため、最終的には必ず主催団体の公式サイトを確認してください。また、日商簿記は紙試験とCBT試験で受験料が異なる点に要注意です。
日商簿記
- 紙試験の受験料(参考)
- 1級:7,710円
- 2級:4,630円
- 3級:2,850円前後
- CBT試験の受験料(参考)
- 2級:7,480円
- 3級:4,400円
- 合格率の目安
- 1級:8~10%(非常に難関)
- 2級:10~30%前後(試験回により変動大)
- 3級:40~50%前後
- 試験方式・会場
- 紙試験:年3回(2月・6月・11月)
- CBT:随時(テストセンター方式)
- 1級は年2回(6月・11月)紙試験のみ
全商簿記
- 受験料
- 1級:会計1,300円+原価計算1,300円(計2,600円)
- 2級・3級:各1,300円
- 合格率の目安
- 1級:35~45%
- 2級:60~70%
- 3級:60%前後
- 試験方式・会場
- 年2回(1月・6月)
- 高校など「試験場校」で実施
全経簿記
- 受験料
- 上級:7,500円
- 1級:1科目2,200円(合計4,400円)
- 2級:1科目1,700円(合計3,400円)
- 3級:1,400円
- 基礎:1,200円
- 合格率の目安
- 上級:20%前後
- 1級:各科目35~60%前後
- 2級:商業簿記は40%前後、工業簿記は80%前後
- 3級・基礎:70%前後
- 試験方式・会場
- 1~3級・基礎:年4回(2・5・7・11月)
- 上級:年2回(2・7月)
- 指定された全国の専門学校等で実施
どの試験が自分に合っている?簡単チェック!
- 【高校生の方】
→ 高校の授業と連携している全商簿記がおすすめ。大学入試の優遇も狙える - 【専門学校に通っている方】
→ 全経簿記がカリキュラムと親和性が高く、税理士試験の受験資格も得やすい - 【大学生・社会人・転職希望者】
→ 履歴書で強みになる日商簿記2級以上の取得が最適。実務評価も高く、安定の人気 - 【将来的に税理士・会計士を目指す方】
→ 日商1級 or 全経上級の合格+大学卒業などの条件を早めに確認しておこう
再就職に強い資格は?専業主婦が成功するための資格選びと活用法
まとめ~自分の目的に合った資格を選ぼう~
- 就職や転職で広く評価されるのは「日商簿記2級以上」
- 商業高校在学中なら全商簿記も有意義
- 専門学校や社会人が全経簿記を利用するのもメリットあり(試験日程が多い、上級で税理士試験受験資格など)
- 日商簿記1級や全経簿記上級だけでは税理士試験受験資格に不十分な場合があり、大学卒業等の学歴要件との組み合わせも必要
- 合格率や受験料は変更される可能性があるため、受験前に必ず公式サイトを確認
いずれの簿記試験も、会計や経理の基礎を体系的に学ぶうえで非常に役立ちます。とくに「転職や就職に直結するスキル」を重視するなら日商簿記が王道ですが、学生時代から全商簿記を取得する、あるいは税理士受験資格を狙って全経簿記上級を活用するなど、目的や学習環境に合わせて自分に合った試験を選ぶようにしましょう。
上記の情報は、あくまでも現時点での一般的な目安や傾向です。合格率や受験料・試験範囲などは随時見直されることがありますので、最新かつ正確な情報は公式サイトで必ず確認してください。自分の目標や学習スタイルに合わせて、最適な資格を選び、ぜひチャレンジしてみてください。
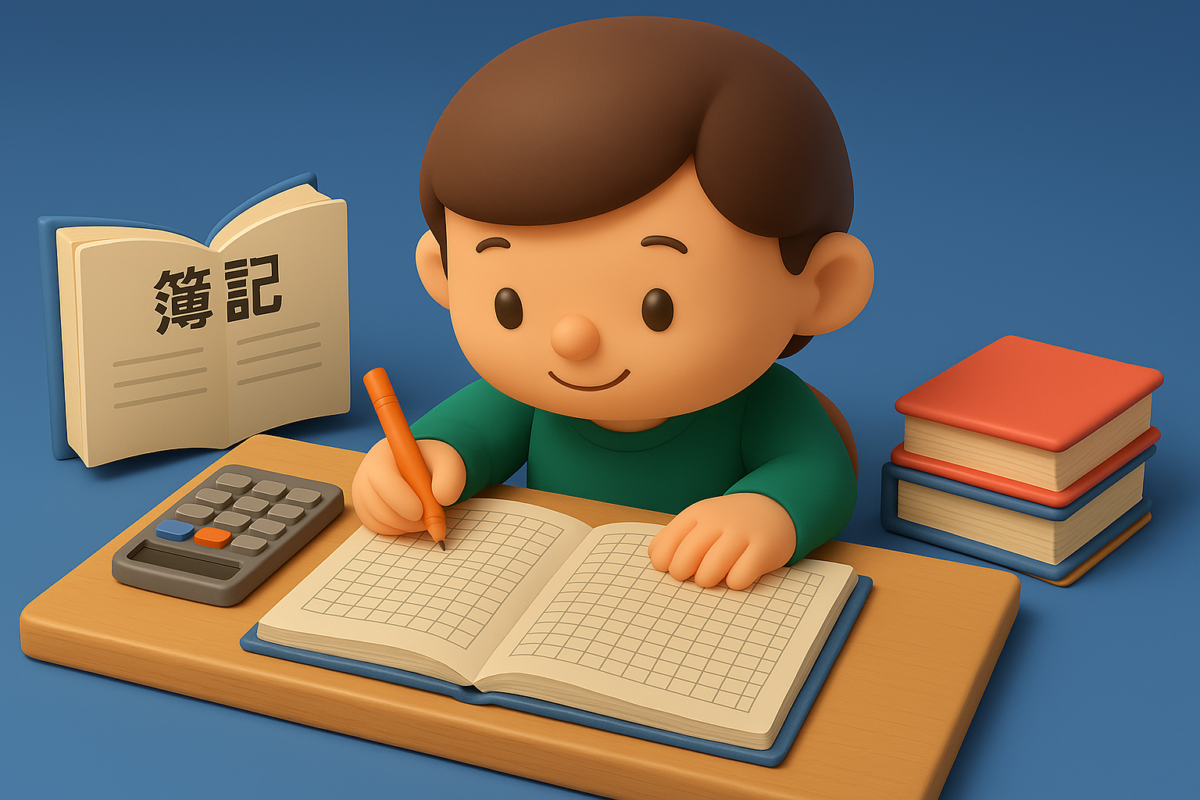
コメント